
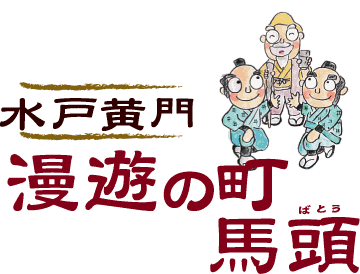
水戸藩の殿様は江戸小石川の屋敷に常住で、光圀公藩主時代の30年間に水戸に帰ったのは只の11度だけ。しれも幕府の許可を得ての帰藩である。
藩主時代の四回、西山に隠居して5回、都合9回の馬頭(水戸領武茂の里)への順村である。なぜだろう?
最も大きな理由は、光圀公が天和3年6月(1683)当地の博学者大金重貞との出合である。
湯津上村の古碑を光圀公に伝え、国造碑堂字の建立、侍塚古墳発掘の指示を受け、光圀公の期待を充分に果
たした。
これを機に、終生に亘る親交を深め、光圀公はたびたび馬頭に足を運ぶことになった。
理由は他にもありそうな謎は黄門様の足跡を散策しながら問うてみませんか。
藤田製陶場・市川窯
水戸藩は御三家の格式、また幕末軍備強化策などで藩財政は極度に遍迫、その対策として斉昭公は殖産振興を施策、その一策として焼物の開窯を計り、 小砂に陶土を発見。日頃の徳政に報いようと村民有志御用瀬戸窯を1851年9月開窯したのが小砂焼の始まり。
以来、有志の努力と技術研さによって今日の小砂焼がある。焼物を手にすると、陶工たちの水戸藩への思いが映される。
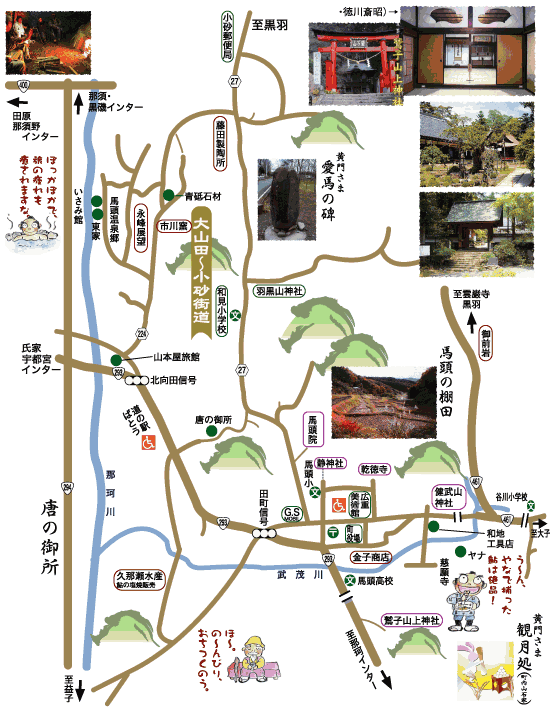
鷲子山上神社(とりのこさんしょうじんじゃ)
八溝山系の霊峰鷲子山は、「日本の自然百選」にも選ばれている。正に自然に恵まれた幽すいは神の依代。
鷲子山上神社がある。光圀公は、延宝元年九月と、元禄八年三月の二回登拝している。そのいずれかの折、鷲子山十景七奇の碑は、九代藩主斉昭公が光圀公の意を対して、侍臣らに建てさせたもの。
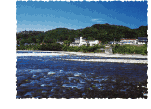
光圀公は、重貞の案内で黒羽に向かう折り(天和三年六月-一六八三)、長峰で茶席を設け休息。四方を展望され小興趣の時を過ごされたとか。長峰は、湯の香ただよう温泉郷。近くに「水戸様御乗馬の碑」などもある。黄門様は、領内名所地で八景を選ばれている。黄門様は、領内名所地で八景を選ばれている。黄門様の八景などに思いを寄せながら、馬頭温泉の湯に身を癒すのも乙なもの。
昔は地蔵院と云われた由緒の深いお寺である。元禄五年六月二十四日(一六九二)、地蔵院を訪れた光圀公が、境内脇堂に納められている馬頭観世音をお調べになられ、馬頭観音を本尊となさるべきと仰せられ、今までの本尊延命地蔵を脇 仏として、院号地蔵院と改められた。なんでだろう?この時、記念に植えられたのが「三度栗」と伝えられ、県指定天然記念物となっている。
宇都宮市一族武茂氏の菩薩寺乾徳寺は、一族の衰微ともに武茂氏の領域(馬頭町域)は、佐竹氏の支配しるところとなった。佐竹氏は、本寺の住僧をこの地に配住。境内を一新明応八年開基として、領内の支配と善導の拠点の寺とした。乾徳寺は、それなりの石高は給されたが、光圀公は一度も訪れることは無かった。なぜだろう?
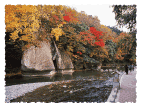
武茂の清流に姿を写す奇岩。「これは美事な出生岩だ」と黄門様。元禄十一年八月十日の事である。自然の造形への称賛と敬神の思いでご覧になった御前岩。
黄門様は、領内の陰陽石神とかかわり崇敬の念を寄せられている。黄門様の御生涯を忍ぶとき、その御心情お察しできる一面 もある。精力・融和と繁栄の神徳御前岩。是非ご参拝を。
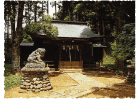 (しずじんじゃ)
(しずじんじゃ)静神社
水戸藩社寺改革の折り、光圀公は八幡社を改め、愛卮山に移し、静神社と名付けられた。(現在地は明治三十三年還宮)春の例大祭の祭屋台で娘の手踊りをご覧になられた 光圀公は、「日射しが強く可哀相だ、 日覆をしては」と仰せられた。とっさの事で、世話人たちはとまどいながら仏事用の白黒の天幕を張って急場を凌いだ。これを「御免天幕」と云って今日まで受け継がれている。
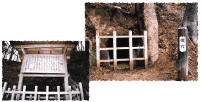
光圀公は、寛文三年(一六六三)十月大山田金山に足を運んでいる。
かって佐竹藩の財政を潤した金山の実状検分である。金の産出は佐竹時代が全盛期で、元禄末期は坑道の下降、湧水対策など、当時の採掘技術では限界に達し、豊富な埋蔵量 があっても衰退となった。
(当時の金山の様子を記した古文書がある)
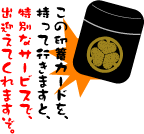
武茂川は、かって砂金「ゆりがね」採取の流城であった。健武地に「古代産金の里」の碑が建つ、金山の神金山彦命を祀る健武山神社がある。那須のゆりがねは、「東大寺大仏鋳造」にもかかわり、採金は役所の直営であった。
黄門様も巡村の折りの道筋、記録にはないが、参拝されたことは間違いない。みなさんも御参拝、近くの「ゆりがねのやな」での御休息は、いかがですか。