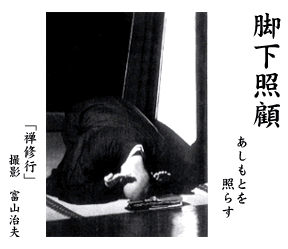| 目次 | |||
| 01-ほとけの道のお誓い(十戒)-諸悪莫作- | 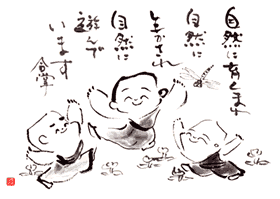 |
||
| 02-見釈迦牟尼仏 | |||
| 03-いのちの伝承(一) | |||
| 04-いのちの伝承(二) | |||
| 05-いのちの伝承(三)死をみつめる | |||
| 06-偶一行修一行 | |||
| 08-脚下照願 | |||
| 09-仏心 | |||
| 10-観無常心(かんむじょうしん) | |||
| 11-浄信一現 | |||
| 12-念念相続 | |||
| 13-此一日の身命は尊ぶべき身命なり | |||
| 14-銀椀に雪を盛り明月に鷺を藏す | |||
| 15-絆 つながって生きる | |||
| ほとけの道のお誓い(十戒)-諸悪莫作- | |||
| まず第一は | |||
| 不 殺 生 戒 ふせっしょうかい | |||
| 人や物のいのちを生かさんと誓います | |||
| 第二は | |||
| 不 偸 盗 戒 ふちゅうとうかい | |||
| むさぼりとらずに 他に喜びを与えんと 誓います | |||
| 第三は | |||
| 不 貧 婬 戒 ふとんいんかい | |||
| 欲するままの行いを慎み自然の摂理を大事に生きんと誓います | |||
| 第四は | |||
| 不 妄 語 戒 ふもうごかい | |||
| 嘘をつかず人の心を潤すような言葉を心がけんと誓います | |||
| 第五は | |||
| 不 酤 酒 戒 ふ こしゅかい | |||
| 元の清らかな心の生地をたもつよう誓います | |||
| 第六は | |||
| 不 説 過 戒 ふせつかかい | |||
| 愛語につとめ 人を引きたてるよう誓います | |||
| 第七は | |||
| 不 自 讃 毀 陀 戒 ふじさんきたかい | |||
| おおらかな心で 生きようとお誓いします | |||
| 祖師方が大切にされた「仏心」が忘れ去られようとしており、依然混迷の様相が増しております。 「見釈迦牟尼仏」――― 仏さまの姿をみつめ、仏さまの言葉に耳をかたむけ、共に喜びたいと示され、仏さまとの出会いこそ生きる礎としていこうと、道元禅師は示されました。 正月の”正”は、”一”度”止”まって今日までの生き方を見つめ直し身の処し方をじっくり考えてみませんか!という歳の始めの月。できることから始めてみましょう。 仏前で静かな時間(坐禅)を 行じてみる 手を合わせ口に唱えて「南無釈迦牟尼仏」(三遍)を 行じてみる 心をこめて合掌、礼拝して般若心経等 読経を 行じてみる 是非、心を発し勇気を出して始めてみましょう。苦悩と共にあるいのちの中で「見釈迦牟尼仏」の心を育てて行くことこそ信仰の道を歩む喜びです。 |
|||
| いのちの伝承(一) | |||
|
|||
| 生まれかわり、死にかわりして数えきれない祖先のいのちが引き継がれ、今、自分のいのちを生きています。 生老病死のこのいのち、どの様に生き、老いを見つめ、病と向き合い、死を迎えるか。この死こそ人としての卒業式。何をもって次の世代にバトンタッチすればいいのでしょう。(これが大難問) まず一つには生きる力。 私の人生を生きぬくための生命力。 人が人らしく生きぬく力。 この力を日常の生活の中に生かし共に学びあい、育てあうことが必要となってくるでしょう。この一つ一つを次世代に残したい、いのちの宝ものです。 弁道話の中に 「仏道をならふといふは 自己をならふなり」 と示されておられます。詳しくは次回に続きます。 |
|||
|
|
|||
| いのちの伝承(二) | |||
| 自分が自分らしく生きるには 今、頂いているこのいのちを見つめることが第一歩。これが生きる力となって輝いて、いのちの真実に出逢うことになります。 では いのち とは 何? 第一 この「いのち」は、天地いっぱいの一つ一つのいのちと、 かかわりを持って生きております。 第二 この「いのち」は、だれとも違うただ一つのもの。 オンリーワン!みんなちがってみんないい!もの。 第三 この「いのち」は、必ず最後に「死」がまっています。 意識してもしなくても、いつどこで死ぬるいのちか わからない。 第四 この「いのち」は、常に変化しています。川の流れのごとく。 今日の自分は、昨日の自分ではなく明日の自分でもない。 このいのち(死)について 考えていくと重苦しい気持ちになるが、真剣に考えていけば、今の「いのち」を大切に、今日という一日が輝いてきます。 |
|||
| いのちの伝承(三)死をみつめる | |||
修証義に「生死は仏の御いのちにて…」と示されております。 |
|||
真澄 拝 |
|||
| 内外共に混迷の様相であります。 | |
| 私共の曹洞宗においては、どんな時代になろうとも、どんな生活の中にあっても大切に保たれなければならないことを、祖師方が示されております。 | |
| 高祖 道元禅師は---『身心自然に脱落す』 | |
| 太祖 瑩山禅師は---『心地を開明し本分に安住せしむ』 | |
| 毎朝のひととき 調身、調息、調心の 心を静かに保つ数分を持ちたいものです。 | |
| そして、ゆっくりと 口に唱えて言わく | |
| なむ しゃか むにぶつ | |
| 『南無釋迦牟尼佛』と三遍お唱えします。 | |
| この発心の一歩こそ、仏さまの教えに値う光明となり、心安らかな生活の基盤となることでしょう。 |
| 一行に遇って一行を修す |  |
| 人生に定年はありません。 | |
| 老後も、余生もないのです。 | |
| 死を迎えるその一瞬まで、人生の現役です。 | |
| 人生の現役とは自らの生を悔いなく生きることです。 | |
| そこには「老い」や「死」への恐れではなく | |
| 「尊く美しい老い」と「安らかな最後」があるばかりです。 |
| 観無常心(かんむじょうしん) |
| 無常を感じることは真実に覚め、 | |
| 無常に出逢うことは真の自分に出逢う | |
| 生まれたものは死に | |
| 会ったものは別れ | |
| 持ったものは失い | |
| 作ったものはこわれます | |
| 時は | |
| 矢のように去っていき | |
| すべてが無常です | |
| この世において | |
| 無常ならざるものは | |
| あるでしょうか | |
| 正しい宗教 | |
| 自分の宗教を信じるあまり他宗をそしり、 | |
| 果ては憎しみ合うほどおろかな事はない。 | |
| 正しい宗教は、いつの時代でも人々を明るく照らし | |
| 平和な身と心のあり方を導くものである。 | |
| 親鸞上人は、 | |
| 「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」といわれました。 | |
| イエス・キリストは | |
| 「心貧しき者、天国はその人のものなり。悲しむ者、その人は慰められん。」 | |
| 道元禅師は、 | |
| 「坐禅は安楽の法門なり」 | |
| 「仏道をならふと言うは自己を習うなり」と言われております。 | |
| 普遍の宗教には、誰でもが等しく普く救われ | |
| 安らかに生きるという道理が示されています。 | |
| 浄信一現 | |
| 亥の新年 おめでとうございます。皆様のご安心、ご清祥をご祈念申し上げます。 私も還暦となり、歴の元に還り再スタートの年となり ました。お檀家の皆様に対しまして御恩酬い難しの感が あり、力不足で申し訳なく思っております。 これから再スタートの誓願で精進いたす所存です。 今後共ご法助の程お願い申し上げます。 道元禅師のお言葉の中に 朝のひとときお仏壇に温かい心のこもったお茶をお供えし、 |
|
| 念念相続 | |
秩父の霊場には とにかく長い階段があります。 経典の中に「念念相続」が示されています。 「常に仏様を 念じて念じて生きる」 過去にとらわれず 未来を求めすぎず 感謝と供養と祈りの相続が 善き方向に進んでいこうと |
|
| 此一日の身命は尊ぶべき身命なり | |
北海道知床半島のお寺に鈴木章子さんと言う方がおられます。 癌は私のみなおしの人生の |
|
| 銀椀に雪を盛り明月に鷺を藏す | |
毎朝六時三十分より、本堂にて、坐禅と朝のおつとめに親しんでおります。最近このひと時に、 |
|
| 絆 つながって生きる | |
毎朝6時30分より、坐禅と朝のおつとめに親しんでおります。 それぞれ人皆違っておりますが大自然の中に抱えられているいのちであります。 中国の禅僧・洞山良价禅師(807〜869)の法語「宝鏡三昧」の句に 朝の数分間、お仏壇の前でこのいのちのつながりを |
|
| back | |