|
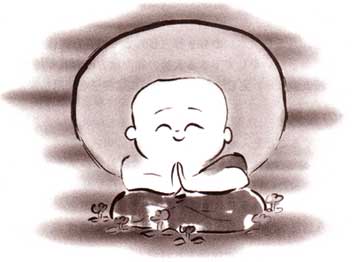
|
|
|
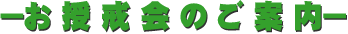
|
| 戒 師 |
前大本山總持寺貫首 板橋興宗禅師 |
| 期 日 |
平成17年10月5日〜9日(5日間) |
| 道 場 |
宇都宮市 祥雲寺(宗務所) |
| 主 催 |
曹洞宗栃木県宗務所 |
|
| |
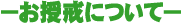 |
|
お授戒(じゅかい)とは、約2600年前にお釈迦様がお説きになられ、達磨大師や、永平寺開山道元禅師様、總持寺開山瑩山禅師様を経て現在の住職まで伝わっている「戒法」があり、この戒法を受け継いで仏弟子の仲間入りをすることです。 |
|
お授けいただいた戒法によって、私たちの心に本来具わっている美しい仏心に一人ひとりが目覚め、お釈迦様と変わりない本来の自己を見いだすことが出来ます。そして仏の御子としての境涯に安住することにより、毎日をこだわりのない感謝の日々として、心豊かに生活してゆくことができるはずです。そのような日々を生きることが人間最上の幸福であると考えます。 |
| この人間として最上の幸福を皆様一人ひとりに見出していただくために、五日間にわたって行われる法要儀式をお
授戒会といいます。お授戒会は、曹洞宗の数多くある法要の中で、最も勝れた且つ重要な法要儀式です。 |

|
| 今回のお授戒会は、梅花流詠讃歌を取り入れたもので、曹洞宗栃木県宗務所主催で宇都宮市・祥雲寺を道場として行われます。戒師に前大本山總持寺貫首 板橋興宗禅師様をお迎えしてのお
授戒会ですので、老若男女を問わず、多くの檀信徒に勝縁を結んでいただきたいと思います。 |
| 日程は平成17年10月5日(水)から9日までの五日間修業いたします。戒師様を中心に、法要のお手伝いをして下さる大勢の和尚様方の
お取り持ちで、盛大にしてかつ厳粛に進められます。尚、全て法要儀式等の際には、椅子を使用します。 |
|
|
 |
|
◆お授戒会に参加することを入戒といいます。 |
◆お授戒会に入戒して、お血脈を受ける皆様を戒弟といいます。男性の戒弟を優婆塞(うばそく)、女性の戒弟を優婆夷(うばい)と
いいます。 |
|
◆戒弟の皆様がお勤めする修業を、特に加行といいます。 |
|
◆お授戒会に集う僧俗へ施しをされることを、供養といいます。 |
| |
| お授戒会に参列されますと、戒師様より親しく仏戒をいただくことになりますが、仏戒の一つ一つが仏様の尊いお心、お徳そのものなのです。しかもそお仏様のお心お徳と同じものが、私たちにも生まれながらに具わっていることに気づかせていただくのが、お
授戒会のありがたさなのです。 |
| お授戒会中お勤めする加行には、「礼仏」と称して和尚様方と一緒に「南無三世諸仏」と声を揃えてお唱えし、一斉に礼拝をする修業があります。そのひたむきな修業の中に、お
授戒会ならではの法悦をしみじみと味わっていただけることと思います。 |
| また、お授戒会の中で最も大切な修業の一つに、「聞法」があります。戒師様に代わり、説戒師様に仏さまの教え、仏戒の一つ一つ
を戒弟の皆様に解り易くおさとししていただきます。 |
| そして仏戒を授けていただく前に、日常生活の中で気づかないまま行っている過ちなどを悔い改める「懺悔」の式をお勤めいたします。 |
一人ひとりが「南無三世諸仏」とお唱えし、お拝をし、説戒の一語一語をよく聞き、自分のものにしていただいて、初めてお血脈を
いただくことが出来るわけです。 |
|
|

|
 |
お授戒会において厳粛に修業をしていただき、仏様のお心とお徳を受け継がれるその証がお血脈であり、授戒した人に付けられる仏弟子としての名がお戒名です。
お血脈やお戒名は、一般的に亡くなられた人のものと考えられているようですが、決してそうではありません。本来戒名とは、授戒名といってお授戒を受けて、仏様のお心とお徳を受け継がれた人だけに与えられる仏の御子としての名前です。従って檀信徒として生前にお戒名を受けて、信仰生活をすることはよりすばらしいことです。 |
|
|
| お血脈を授けられ、お戒名を受けられた日より以後、皆様は、仏の御子となります。戒を今後の人生の指針として仏弟子としての名の相応しい生き方をしたいものです。これこそが真の幸福への道なのです。お
授戒会とは、誠にありがたいものです。 |
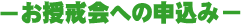 |
曹洞宗栃木県宗務所主催による梅花流詠讃歌を取り入れたお
授戒会は、初めてのことですので、その有り難き尊い因縁を大切にしていただき、より多くの人に仏様との深いご縁を結んでいただきたいと思います。ご家族はじめご親戚、ご友人の方々もご一緒に申し込んでいただきたく、ご案内申し上げます。
お授戒会に参加してお血脈を受けることは、老若男女を問わずどなたでもできます。ただし、満15歳以上の方とさせていただきます。また、既にお血脈お戒名をお持ちの方も受けられます。これを再
戒といい、徳は重なるほど尊いものです。 |
 |
お授戒会の期間中、諸法要儀式に参列され、戒名を頂き、戒師様の手から直接お血脈を受けられる方を正戒といいます。正戒の方は、五日間を通して参列していただくのが本義ですが、今回は道場の都合で、第3、第4、第5日目の三日間【金、土、日
曜)をあてます。宿泊されるのが原則になります。但し、都合により自宅から通われる方、外泊されて通われる方も可とします。(旅館等の手配は宗務所でも可能ですが、費用は自己負担となります)通いの方は、午前8時上山、午後7時下山の予定です。勧募人員は、150名を予定しております。 |
|
 |
因戒とは、お授戒会に一日だけ参列され、戒師様とご法縁を結ばれ、またいつの日かお授戒会に参加できるように因縁を作っておくことをいい、お血脈
をいただきます。戒名はいただきません。お授戒会中の第1、第2日目(水、木曜)をあて、午前9時上山、午後5時下山の予定です。勧募人員は、各日200名、計400名を予定しております。 |
|
|
 |
亡戒とは、既に亡くなられた方に、お受戒会の尊い功徳をご供養するためのもので、期間中特別にご回向(えこう)をして正戒と同じくお血脈をいただきます。勧募霊数は、500霊を予定しております。 |
|
| |
|
◆戒金について |
|
戒弟1名につき、下記の戒金を申し受けます。 |
|
・正戒…1名につき 金30,000円 |
|
・因戒…1名につき 金10,000円 |
| ・亡戒…1霊につき 金
5,000円 |
|
|
◆その他、出来うる限り戒弟の方のご都合にご希望に便宜を図りたいと考えております。入戒についてのご相談がありましたら菩提寺、または宗務所までおねがいいたします。 |
|

|
|
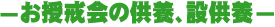 |
|
お授戒会中に、特にご供養の法座を設けております。お授戒会に集う僧俗の方々への供養の施主になられることは、この上ない菩提心の発露であり、ご先祖様方へのなによりの報恩供養であります。 |
お授戒会中のご供養は、二通りの法座を設けております。
| ・一つは、「御親香供養」といい、戒師様が
導師を勤める法要です。 |
| ・一つは、「ご供養」といい、教授師様や引請師様やお役目の御老師様が導師を勤める法要です。 |
|
|
お昼前に行う法要を午時供養といい、午後に行う法要を晡時供養といいます。御先祖のためにお授戒会参加の大勢の僧侶が一堂に会して読経を勤めてくださるのはお
授戒会をおいて他にはなく、施主としての感銘と悦びは終生の感激であり、宝ともなりましょう。 |
| ・さらに「設供養」といい、授戒会参集の僧俗に食事を差し上げる供養があります。設供養は食事の時のお唱えにご先祖様の戒名を読み込んでいただき、参加者全員の合掌の中、食事の施主として堂中を廻ります。いずれの供養もありがたく尊き因縁ですので、ご家族にてご相談の上、申し込んでいただきたく、ご案内申し上げます。 |
|
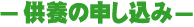 |
| □ 供養、設供養 |
供養は、ご先祖様への何よりの報恩行であります。供養は初日から4日目まで、設供養は、5日目まで設けておりますので、申込書を参考にご都合のよい日と法座をお選びいただきます。勧募法座数は御親香供養八座、ご供養四座を予定しております。
設供養は食事ごと十二座あります。 |
|
□ 供養料は下記の通りです。 |
| ・御親香供養… 1供養につき 金500,000円 |
| ・ご 供 養……
1供養につき 金200,000円 |
| ・設 供 養…… 1供養につき
金 50,000円 |
|
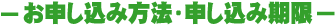 |
|
□ |
入戒を希望される方は「正戒申込書」「因戒申込書」「亡戒申込書」に必要事項を楷書で明記の上、戒金を沿えて菩提寺へ申し込んでください。 |
|
□ |
供養を希望される方は、「供養申込書」「設供養申込書」に必要事項を楷書で明記の上、菩提寺へ申し込んでください。供養料の納入については、別途通知いたします。 |
|
|
□ |
その他ご不明な点は、菩提寺、又は宗務所へ直接お問い合わせください。 |
|
□ |
5月31日までに、菩提寺へお申し込みください。 |
|
□ |
申し込まれた方には、追って詳細をお知らせいたします。 |
|
|
|
以上、お授戒会の尊さ、ありがたさ、功徳について説明させていただきました。
皆様是非お誘い合わせ、ご参加下さいますようご案内申し上げます。
乾徳寺:TEL 0287-92-2247 |